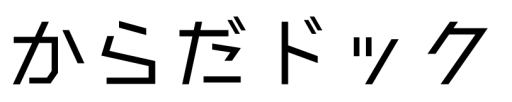Proposed by Yujiro Nishiyama, Japan.
第1章:「分類が変わる」ということ ― 書痙の歴史から見る、新しい視点
かつて、「書痙(しょけい)」という症状は“心の問題”だと考えられていました。
プレッシャーや緊張が原因で、手が震えたり、文字が書けなくなったりする。つまり、精神的ストレスによる一時的な不調だと。
しかし研究が進むにつれて、脳の運動を司る領域(特に大脳基底核や感覚運動野)に、明確な活動異常があることがわかってきました。
つまり、「心のせい」ではなく、脳の中で“誤った運動プログラム”が作られてしまっている状態。
これが、書痙が「精神疾患」から「神経疾患」へと再分類された瞬間でした。
この流れは、医学における「分類の進化」を象徴しています。
「これまで“同じもの”だと思われていた現象の中に、実はまったく異なる仕組みが隠れている」
私は、局所性ジストニアの中にも、まさにこの“もう一つの仕組み”が存在していると考えています。
それが私の提唱する――局所性ジストニズム(Local Movement Dystonism:LMD)です。
第2章:局所性ジストニズム(LMD)とは何か
■ 定義
局所性ジストニズム(LMD)とは、私、理学療法士の資格を持つ西山祐二朗によって提唱された新しい運動制御概念であり、
従来「局所性ジストニア(Focal Dystonia)」に分類されてきた症例の中で、
- 相反神経抑制の過活動(拮抗筋制御の誤り)
- 感覚統合の乱れ
- それに伴った筋力低下
を主な特徴とするものを指します。
この現象は「神経疾患」ではなく、誤った運動学習プログラムによって生じる可塑的な現象と考えられます。
LMDは「壊れた神経」「元に戻らない状態」ではなく、「再教育できる神経回路」の問題である。
■ 脳の仕組みとの関係
人は動きを「筋肉」ではなく「脳の地図」でコントロールしています。
LMDは、この地図が誤って書き換えられた状態――つまり、脳の誤学習によって起きている現象です。
だから、脳のプログラムを再教育する必要があります。
そのためには、動きを作り出すための最低限の筋力が必要になります。
第3章:単関節リトレーニング(OJR)の理論的背景
LMDを改善するための理論体系が、単関節リトレーニング(One-Joint Retraining:OJR)です。
■ 定義
OJRは、理学療法士の西山祐二朗によって開発された運動感覚再教育法であり、
単関節運動(One-Joint Movement)を用いて、過剰な制御や誤った神経プログラムをリセット・再構築することを目的とします。
このアプローチでは、
1つの関節の動きに意識を集中させ、
最小限の動作で正しい筋協調を再学習させることを重視します。
OJRは、LMDに見られる「力が抜ける」「思った通りに動かない」「固まって動かない」などの運動時に起こる現象を、
神経筋再教育(neuromuscular re-education)によって改善するための、最も基礎的な手法です。
■ OJRを支える3つの理論的柱
- 神経可塑性(Neuroplasticity):脳は一度学んだ動きを修正し、再構築できる。
- 相反神経抑制(Reciprocal Inhibition):片方の筋肉を動かすと、反対側は自然に抑制される。
- 注意と意識の方向性(Focus of Attention):意識の置き方によって筋活動パターンが変化する。
これらを単関節運動という最も純粋な形で再教育するのがOJRのコアです。
第4章:あるピアニストの手(症例エピソード)
10年以上前から、右手の小指が巻き込み、潰れ、中指が突っ張ってしまうと悩んでいたピアニストがいました。
彼女はとある整形外科で「局所性ジストニア」と診断され、激しい練習をやめるよう言われていました。そして、ゆっくり一本ずつ動かす練習をするよう言われていました。それで少しずつ改善していったそうですが、速い曲になるとうまく弾けなかったそうです。
しかし、OJRのプロトコルを用いて単関節ごとに1つ1つ丁寧に再訓練と再教育した結果、
彼女の指は再び“思い通りに動く感覚” “小指が潰れずに支えている感覚”を取り戻しました。
この過程から考えられるのは、ゆっくり動かすことでも分離運動はある程度までならできるようになる。しかし、ff (フォルテッシモ)のように速く強く弾く時には、筋力が必要だったということ。そして、
彼女の「動かそうとする意識の向け方」が変わったことがとても大きな変化を出したのだと思います。
第5章:LMDが示す新しいパラダイム
医学は「過剰に興奮している脳を抑制する」方向で研究されています。
しかしLMDが示すのは「過剰興奮している部分があることで、反対に抑制されている部位を賦活することで、過剰興奮を整える」という真逆のアプローチです。
私が提唱するのは“治療”ではなく“再教育”。
そしてあなたは“患者”ではなく“学習者”です。
第6章:世界へ ― LMDとOJRの定義(英語版)
Local Movement Dystonism (LMD) is a re-educable maladaptive motor learning phenomenon,
characterized by weakness, abnormal co-contraction, and disturbed reciprocal inhibition.One-Joint Retraining (OJR) is a re-education method designed to reset and rebuild
the motor control system through isolated, conscious, one-joint movement.Proposed by Yujiro Nishiyama, Japan.
結び ― 動きを取り戻すことは、生き方を取り戻すこと
動きや姿勢には、その人の「生き方」や「考え方」が表れます。
間違って覚えた動きを正しく学び直すという行為は、自分の身体と向き合い、もう一度“自分らしさ”を取り戻す過程でもあります。
局所性ジストニズムは、その入口にすぎません。
私たちは幾つになっても、動きを通して、脳を、そして生き方を再教育できると考えています。